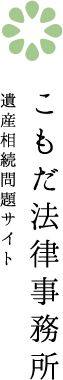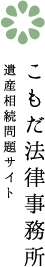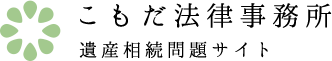第1 「高齢化社会」への備え
1 昨今、日本は「高齢化社会」を迎えつつあるなどとと言われて既に久しくなってきましたが、未だに私たちを取り巻く社会意識のレベルでは、「父母や身近なお年寄りに、もしものことがあった場合のための対策」を考えたり、準備したるすることは言い出すことさえ憚られてしまうような風潮が一般的です。
その結果、実際に父母に「物忘れ」が目立つようになったり、時間や場所の認識がずれているなどの症状が出始めたため、「認知症」が疑われるようになってしまった後で、慌てて父母の「財産の管理」や「遺産の相続」などについて対策を講じようとしても、「とき既に遅し!」の状態になってしまっていて、有効な対策などを執ることが出来なくなってしまっている令和が大変多くなっているのではないでしょうか。
2 このような事案では、ご家族が申立人になって、家庭裁判所に「成年後見人」を選任して貰うような審判の申立てをして、認知症の父母の老後の財産の管理をお願いすることが多くなっているのが現状です。
ところが、そのようにして選任された「成年後見人」の権限というのは、あくまで「現状維持的な財産管理」に留まりますし、被後見人である父母が亡くなると同時に、このような「成年後見人」の権限も消滅してしまうという難点があります。ですから、結局、父母の「遺産の相続」については、残された相続人間で、遺産分割の協議や調停をするという作業が残ってしまいます。
3 そこで、被後見人の遺産について調査を始めてみると、(1)例えば長年認知症の疑いがある父母と同居して面倒を見ていた長兄などが、そのような父母を公証人役場に連れて行ったり、あるいは公証人に自宅や介護施設に出張して貰って、父母に「自分が死亡の時に持って遺産はすべて長兄に相続させる。」というような内容の「公正証書遺言」を作成させていたりする事案が最近特に増えてきています。そうすると、「遺産分割協議」や「遺産分割調停」をする前に、そのような父母が作成した遺言書は、認知症のために「遺言能力」が無い状態で作成されたものだから「無効」だと言って争う必要があり、裁判所の判決で「公正証書遺言」の無効が認められて初めて、父母の「遺産」をどのように分割するのかの協議や調停が出来ることになります。
また、よくある事例として、(2)長年父母と同居して面倒を見てきた長兄やその配偶者が、父母の生前中に、通常の医療費や生活費などの必要性を遙かに超えるような多額な金額を、父母名義の預貯金の口座から引き出して費消しているような事例も増えてきているようです。
さらに、遺産相続の場合にはいつも十分検討しておかなければならないことは、(3)「相続税」のことです。この点は、当職も十分に配慮する必要性を感じていますので、いつも当職が提携している公認会計士や税理士に相談するようにしています。
4 以上のような問題提起を踏まえて、以下には、当職が、日々の経験から、最近増えてきていると感じている事案について紹介しながら、その対策などについて検討してみたいと思います。
第2 「終活」の勧め
1 前項の「高齢化社会への備え」では、高齢の父母のことを心配している子供達や身近な人の方向から「高齢化社会」への備えについて考えてみましたが、今回は逆に、高齢になりつつあることを自覚している世代の方々の方向から検討してみましょう。「脳梗塞」や「認知症」というのは、決して他人事ではありません。その意味では、まさに「そんなことになるのが昨日や今日のこととは、思わざりけり。」なのです。
2 このような発想から、当職は、かなり前から、「終活」を提案してきています。 ここに「終活」というのは、要するに「自分が未だ元気なうちに、自分が死ぬまでのことや自分が死んだ後に子供達に承継してほしいことまどについて予め準備しておく。」ということです。
3 この点、最近になって「エンディングノート」を書いておきましょうということが盛んに言われるようになり、色々な種類のノートが市販されるようになってきています。この「エンディングノート」というのは、「自分が死亡したり、判断能力や意思疎通能力を失ってしまうような病気にかかったときに、自分に関する情報(例えば、預貯金や株式、投資などの財産や貴重品に関する情報)や希望する内容(例えば、延命措置を臨むか望まないか、葬儀に関する希望など)を予め書き留めておくためのノート」のことです。つまり、自分に関する情報を、身内の方に分かり易く書いて残しておくという役割を持ったノートということです。従って、「エンディングノート」は、あくまでも任意に「心覚えのため」に作成しておくもので、「遺言書」とは違って法的な効力はありません。ただ、自分の存命中や死後の家族の負担を軽減するという目的で作成するものです。
ところが、いざ「エンディングノート」を書こうとしても、なかなか筆が進まないのが現状のようです。そこで、当職は、法的な専門家の立場から、その「エンディングノート」の選択から作成の援助をしてお手伝いをさせて頂いたらどうかなと考えていますので、ご相談下さい。
ただ、「エンディングノート」の性格から、どうしても家族構成や預貯金・投資等の個人的な事柄をお聞きすることになりますので、別途ご紹介する「公正証書遺言」の作成や、「任意後見契約」、「見守り契約」、「死後事務委任契約」などの利用についても検討して頂く必要がありそうです。
第3 遺言や任意後見契約について
1 まず、「遺言」について考えて見ましょう。
(1)「遺言」とは、法的な定義では、「自然人が、自分の死後のことについて、一定の法的効果を求めて、一定の方式により文字などにして残す意思表示のことで、その人の死後に、その最終意思に法的効果を認めて、その実現を法的に保障する制度のこと」とされています。
(2)このように、「人が亡くなった後に、その最終意思に法的効果を認める制度ですから、その最終意思の内容を正確に保存する必要性があります。
そのために「遺言」として有効であるためには、「厳格な要式」が要求されていて(民法960条)、法律が規定している様式を満たしていない遺言は、原則として「無効」になってしまいます。
法律は、「普通方式」として、①自筆証書遺言(民法968条)、②公正証書遺言(民法969条)、③秘密証書遺言(民法970条)の3種類を認めています。このいずれの遺言書でも共通して(イ)「遺言能力」があることが必要です(民法961条)(この点は、前項で、事例などで、「遺言能力」が無い人が作成した遺言は無効になることを紹介しました)。
また、(ロ)「共同遺言」は禁止されていますしています(民法975条)。つまり、夫婦が同じ遺言書で遺言するということは出来ず、そのような遺言は無効になります。また、(ハ)遺言の内容としても、遺言できる事項が制限されているので(民法902条、908条、964条、781条などの法定遺言事項参照)、注意が必要です。
(3)ところで、遺言書を作成する前に知っておかなければならない事項について、検討しておきます。
まず、(ア)自分の「相続人は誰か。」です。
この点民法は、「血族相続人」(順位あり・民法887条・889条)と「配偶者」(民法890条)と定めています。ただ、この「血族相続人」が自分よりも先に亡くなっていた場合には、「代襲」して相続する「代襲相続人」が定められています(民法887条2項・889条2項・901条)。
次に、(イ)それぞれの相続人は、それぞれ「法定相続分」が定められています(民法900条)。従って、遺言書が無い場合には、この割合によって遺産分割がなされることになることが多いようです。
ただ、法は、相続人のうちに、特にたくさんの「受益」をした人がいる場合には、「持ち戻し」をさせたり(民法903条)、逆に被相続人の介護やお世話をしたような「特別に寄与した人」がいる場合には寄与分をプラスするというような配慮をしています(民法904び2、1050条)。
さらに、(ウ)「遺留分」の制度(民法1042条以下)にも注意しておく必要があります。これは、たとえ被相続人が遺言をしても、一定の相続人(すなわち「兄弟姉妹」を除く相続人(「子」、「直系尊属」、「配偶者」)のために、一定範囲の遺産を残しておくための制度です。つまり、被相続人は自分の財産を自由に処分することができるのが原則ですが、政策的に一定の相続人の生活の保護のために、法律上必ず残しておかなければならない相続分の一定割合(直系尊属のみの場合は3分の1、その他は2分の1)を「遺留分」として侵害出来ないようにしたのです。すなわち、「遺留分権利者」は、遺言によって遺贈を受けた人や相続開始前1年内に多額の贈与を受けた人に対して、自分の「遺留分」を侵害された金額の範囲内で金銭の支払いを請求することが出来ます(民法1046条)。
但し、この「遺留分侵害額請求権」は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈が合ったことを知ったときから1年間行使しないと消滅してしまうので、注意が必要です(民法1048条)。
2 次に、是非知っておきたい「任意後見制度」について見てみましょう。
(1)これは、高齢化社会を迎えて、「法定後見制度」とともに、個人の「自己決定権」を尊重するために、従前の「禁治産者」制度に代わる制度として、平成12年4月1日から施行された「任意後見契約に関する法律」によって創設された制度です。すなわち、自分が不幸にして脳梗塞や認知症などによって判断能力が低下した場合に備えて(任意後見契約法2条)、予めそういう状態になった自分に代わって財産を管理して貰ったり、介護やその他の必要な契約を結んで貰ったりすることを、信頼できる人(例えば、親族や弁護士)に頼んでおく契約をしておくもので、「公正証書」によって作成される必要があります(任意後見契約法3条)。
(2)その任意後見人の活動は、家庭裁判所が「任意後見後見監督人」を選任した時に開始する仕組みになっており(任意後見契約法2条)、公的な監督が為されるようになっています。
(3)その委任の仕方には、以下の3類型があります。
ⅰ)将来型(同時に発行するまでの間の「継続的見守り契約」を結んでおく。)
ⅱ)即効型
ⅲ)移行型(実務では、「任意後見契約」を締結すると共に、それまでの間の「財産管理契約」を同時に締結しておく。)
(4)任意後見人に依頼する代理権の範囲については、予め定めておく場合のほか(日本公証人連合会作成の「代理権目録」参照)、後見事務の実施のための指針として、「ライフプラン」や「あんしんノート」を書面で作成して任意後見人に渡しておく場合があります。
(5)ただ、委任者(本人)の死亡後に医療費や施設利用費などを支払ったり、地代や家賃を支払ったり、葬儀や埋葬等に関する事務を行って貰うためには、「死後の事務処理に関する委任契約」も締結しておく必要があります。
そして、委任契約は、原則として委任者の死亡によって終了するのが原則ですが(民法653条1号)、このような委任者の死亡によっても委任契約が終了しない旨の合意が含まれているような場合には、委任契約は効力を失わないとする判例が出されています(最判平成4年9月22日・金法1358号55頁)。
弁護士 薦田 純一
監事「京都府柔道整復師会」